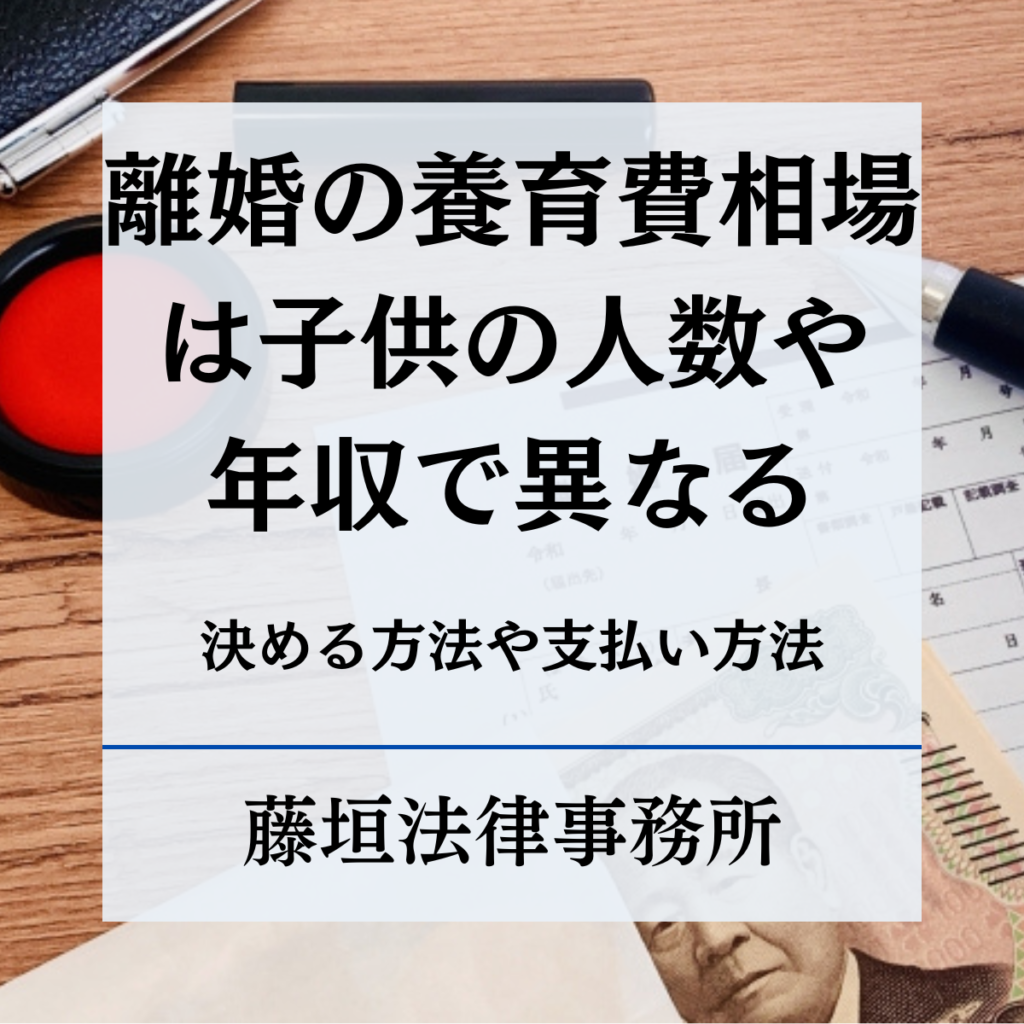
離婚を決意したものの、養育費がどのくらい支払われるべきか悩んでいる方は多いでしょう。養育費の相場は、子どもの年齢や親の収入などさまざまな要素で変動します。
本記事では、離婚の養育費相場や費用が変動する要素、支払い方法なども解説します。
藤垣法律事務所では、離婚の養育費に関する相談を承っており、経験が豊富な弁護士が迅速に対応いたします。
初回相談が無料で、以下からお問い合わせ可能ですので、お急ぎの方はぜひこちらから相談予約してみてください。
目次
一般的な離婚の養育費相場

離婚における養育費の相場は、一般的には平均2〜10万円です。
金額の幅が広く感じるかもしれませんが、個々の家庭の事情や子どもの年齢、親の収入により異なることが関係します。
特に子どもが小さいほど養育費の負担が軽く、年齢が上がるにつれて教育費や生活費が高くなるため、養育費も増加する傾向にあります。
また、複数の子どもがいる場合や、片方の親の収入が大きい場合は、それに応じて養育費の額も変動する要因です。
養育費の算定には、家庭裁判所が作成した「養育費算定表」が参考にされることが多いです。
養育費算定表の概要

ここからは、養育費算定表に関する以下2つの内容について深掘りしていきます。
養育費算定表とは
養育費算定表の使い方
ぜひ参考にしてください。
養育費算定表とは
養育費算定表とは、家庭裁判所が提供する、養育費の算定基準を示した表です。
これは、離婚や別居後に親が支払うべき養育費の金額を、親の収入と子どもの年齢に基づいて公平に決定するための参考となります。
| 年齢 / 収入 | 300万円以下 | 500万円以下 | 700万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 |
| 0〜2歳 | 3〜4万円 | 4〜5万円 | 5〜6万円 | 7〜8万円 | 9〜10万円 |
| 3〜5歳 | 4〜5万円 | 5〜6万円 | 6〜7万円 | 8〜9万円 | 10〜11万円 |
| 6〜8歳 | 5〜6万円 | 6〜7万円 | 7〜8万円 | 9〜10万円 | 11〜12万円 |
| 9〜11歳 | 6〜7万円 | 7〜8万円 | 8〜9万円 | 10〜11万円 | 12〜13万円 |
| 12〜14歳 | 7〜8万円 | 8〜9万円 | 9〜10万円 | 11〜12万円 | 13〜14万円 |
| 15〜17歳 | 8〜9万円 | 9〜10万円 | 10〜11万円 | 12〜13万円 | 14〜15万円 |
参考:裁判所「養育費算定表」
年収ごとの範囲で養育費の目安を示しています。
例えば、年収が300万円以下の父親・母親の場合、子どもが0歳〜2歳の場合、養育費は月額3〜4万円程度とされています。
年収が高くなるほど、養育費の金額も増加する仕組みです。
養育費算定表の使い方
養育費算定表はあくまで目安であり、実際の養育費額を決定するための一つの参考として使用されます。
使い方としては、まず、親の年収を算定表に照らし合わせます。年収は通常、税引き前の総収入をもとにすることが一般的です。
年収が分かれば、次に子どもの年齢を確認します。子どもの年齢も養育費の金額に大きく影響しますので、年齢ごとの目安金額を参考にします。
例えば、0歳〜2歳の子どもを持つ場合、年収が300万円以下であれば、養育費の目安は月額3〜4万円程度です。
ただし、養育費算定表をそのまま適用することが必ずしも適切とは限りません。
算定表はあくまで一般的な基準を示すものであり、各家庭の事情や特別な支出、または親の経済状況によって調整が必要です。
離婚の養育費に影響する項目

離婚の養育費に影響する項目として挙げられるのが、主に以下4つの要素です。
- 子供の人数
- 親の年収
- 再婚や養子縁組の有無
- 義務者の職業
詳しく解説します。
子供の人数
離婚時における養育費の決定には、子どもの人数が大きく影響します。一般的に、養育費は子どもの数が増えることで、その金額も増加する傾向にあります。
理由は、複数の子どもを養育するためには、1人分の養育費に加えて、更なる生活費や教育費、医療費などがかかるためです。
特に子どもの年齢や必要な支出が異なるため、人数が多ければそれだけ養育費の額が増加するでしょう。
養育費は、子どもの人数に比例して大きくなりますが、子ども一人と二人では、1.4~1.5倍程度の差が生じる場合もあります。子どもの年齢が15歳以上だと、金額の差はより大きくなる傾向にあります。
親の年収
養育費は、親の経済的な状況に基づいて決定されるため、年収が高い親はそれに応じた養育費を支払う義務が生じることが一般的です。
具体的には、養育費算定表において親の年収がどれだけ養育費に影響を与えるかが示されています。
親の年収が高ければ、それに伴って子どもの養育にかかる費用も多くなるため、支払うべき養育費の額も高くなります。
一方で、年収が低ければ、支払う養育費は少なくなることが一般的です。ただし、年収が低くても子どもの生活に必要な最低限の養育費は確保されるように配慮されます。
養育費を支払う側(義務者)の年収に2倍の差がある場合、養育費の金額にも2倍近くの差が生じることが少なくありません。受け取る側(権利者)の年収差は、義務者の年収差ほどの影響は見られませんが、年収が大きいほど養育費が小さくなります。
再婚や養子縁組の有無
再婚した場合、一般的に再婚相手には前婚で生まれた子どもに対する法的な養育費義務はありません。
しかし、経済的な状況が変わることが多いため、その影響が養育費の額に反映されることがあります。
再婚によって家庭の収入が増えると、養育費を支払う側の経済状況が改善する可能性があり、それに伴い養育費が増額されることが考えられます。
逆に、再婚相手が経済的に困難な状況であれば、支払うべき養育費が減額される可能性もあるのです。
養育費を受け取る側(権利者)が再婚や養子縁組をして他の養育者が現れた場合、養育費の支払義務自体がなくなる(金額が0円になる)可能性も大いにあります。
義務者の職業
義務者の職業によって、収入の安定性や額が大きく異なります。
職業が影響する大きな点は、収入の水準です。例えば、高収入の経営者や上級管理職などは、安定した収入を得ている場合が多く、その分養育費の支払い能力が高いと見なされます。
一方で、フリーランスや歩合制の仕事、アルバイトなど収入が不安定な職業では、収入の変動が大きいため、養育費の額が変動する可能性があります。
収入が安定していない場合、養育費の額は低めに設定されることがあるでしょう。
給与所得者より自営業者の方が、低い金額で大きな評価がされる傾向にあります。義務者が自営業者の場合、年収が比較的低くても養育費が大きくなりやすく、権利者が自営業者の場合、年収が低めでも養育費は小さくなりやすいです。
離婚の養育費を決める方法
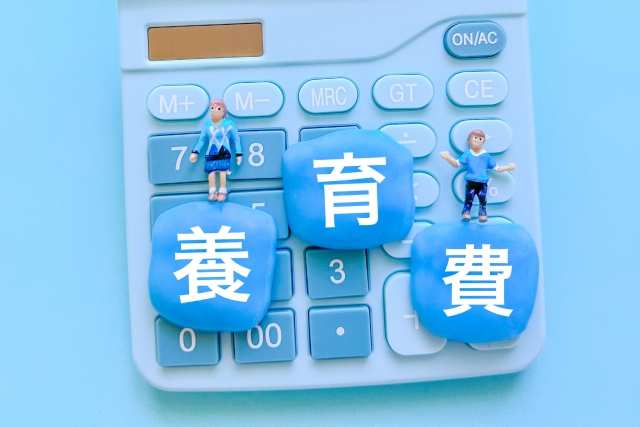
離婚の養育費を決める際、以下の方法で確定します。
- 父母で話し合いを行う
- 離婚協議書を作成する
- 公正証書を作成する
- 家庭裁判所に養育費請求調停の申し立てを行う
- 離婚訴訟を行う
詳しく解説します。
父母で話し合いを行う
養育費を決める方法の1つに、父母での話し合いがあります。
話し合いを通じて養育費の額を決定する利点は、両者が合意した内容にもとづくため、柔軟かつ迅速に決定ができることです。
まず、父母が話し合う際には、お互いの収入状況や生活費、子どもの教育費など、必要な支出項目について具体的に共有する必要があります。
双方がどのくらいの額を支払うことができるのか、またどのように養育費を分担するかを決めるためには、現実的な支払い能力を踏まえた議論が大切です。
話し合いでは、感情的な対立を避け、冷静に子どもの最善の利益を中心に据えた合意形成を目指すことが求められます。
現実に支払が長期間継続できることは、子どものためにも非常に重要なポイントです。そのため、支払の具体的な方法や継続の見通しを踏まえて話し合うことが望ましいでしょう。
離婚協議書を作成する
離婚協議書とは、離婚に関する条件を双方が合意した内容を文書にまとめたものです。
養育費の額や支払い方法、支払い期間などの詳細を明確に記載します。
この協議書を作成することにより、後々のトラブルを防ぎ、養育費の支払いに関する双方の責任を明確にできます。
離婚協議書を作成する際には、養育費の金額をはじめとする基本的な取り決めを具体的に記載することが大切です。
このとき、双方の収入や生活費、子どもに必要な教育費などを考慮に入れて現実的な額を設定します。
また、支払い方法や支払い期間についても詳しく記載することも必要です。
離婚協議書の内容には法的拘束力が生じ得るので、内容が曖昧不明確にならないよう注意しましょう。複数の解釈があり得る記載をしてしまうと、後のトラブルにつながる恐れがあります。特に、金額や支払時期・方法の記載は要注意です。
公正証書を作成する
公正証書とは、公証人が作成し、法的効力を持つ文書のことです。
養育費の支払いに関する取り決めを正式に記録するために利用され、双方の合意が法的に認められる形で保存されます。
養育費の額や支払いの方法、支払いの期間について双方が合意した内容を公正証書に記載し、支払い期間や終了時期、支払いの開始日についても詳細に記載しましょう。
公正証書の作成は、裁判をしなくても強制執行ができるという点に大きなポイントがあります。もっとも、「強制執行認諾文言」が設けられている必要があるため、強制執行のために公正証書を作成する際には漏れがないよう注意しましょう。
家庭裁判所に養育費請求調停の申し立てを行う
夫婦間で養育費に関する合意が得られなかった場合や、話し合いで解決できない場合に家庭裁判所に養育費請求調停の申し立てを行う必要があります。
家庭裁判所を通じて調停を行うことで、公正な第三者である調停委員の助けを得て、養育費に関する取り決めを進められます。
養育費請求調停は、まず家庭裁判所に申し立てを行うことから始まります。この申し立ては、所定の手続きを経て行うことが必要です。
申し立てを行った後、裁判所から通知が届き、双方の当事者に対して調停期日が指定されます。
その後、調停委員が双方の意見を聞き、必要に応じて中立的な立場で調整を行います。調停の場では、養育費の額や支払い方法、支払い期間などが話し合われます。
調停は、調停委員という第三者を挟んで行う協議であるため、中立的な調停委員に十分な理解や共感が得られるような主張を準備することが重要です。具体的には、現在の経済状況を詳細に把握してもらうよう努めるのは有力でしょう。
離婚訴訟を行う
離婚訴訟は、夫婦間で養育費に関する合意が得られず、調停でも解決が見込めない場合に選択される最終的な手段です。
訴訟を提起する際には、まず相手方に対して養育費を支払うよう求める内容で訴えを起こし、その証拠や根拠を提出します。
この証拠には、両親の収入状況や生活費、子どもの必要経費など、養育費の算定に必要な情報が含まれます。
訴訟の結果、養育費の支払い額や支払い方法が決定されると、その内容は判決として記録されます。
判決は法的効力を持ち、双方に対して強制力が生じるため、相手方が養育費を支払わない場合には、強制執行手続きを行うことが可能です。
離婚訴訟は、調停を試みて不成立となった場合にのみ選択できます。また、法律上の離婚事由がなければ離婚自体が認められず、養育費も生じないことになるため注意しましょう。
離婚の養育費の支払い期間

離婚後の養育費の支払い期間については、一般的に「子どもが自立するまで」とされていますが、具体的な期間は子どもの年齢や事情によって異なります。
その1つの目安として挙げられるのが、成人の有無です。
近年、成人年齢が18歳に引き下げられたことで、子どもが18歳に達した時点で養育費の支払いが終了するケースが多い傾向にあります。
ただし、大学進学を希望する子どももいるため、そのような場合は成人後も支払いが続くこともあるでしょう。
特に大学生であれば、22歳ごろまで支払いが続くケースが多いです。
離婚の養育費に関するご相談は弁護士に!
離婚の養育費相場は、子供の年齢や親の年収、職業などによって変動しますが、裁判所が定めている養育費算定表に記載されている金額が目安となります。
一般的に養育費は、父母で話しあって決めますが、揉めるケースも少なくありません。
もしなかなか離婚の養育費支払いに応じない場合は、弁護士への相談もおすすめです。
藤垣法律事務所では、離婚の養育費に関する相談を承っており、経験が豊富な弁護士が迅速に対応いたします。
初回相談が無料で、以下からお問い合わせ可能ですので、お急ぎの方はぜひこちらから相談予約してみてください。

お問い合わせ
法律相談のご希望はお気軽にお問い合わせください
※お電話はタップで発信できます。メールは問い合わせフォームにアクセスできます。



