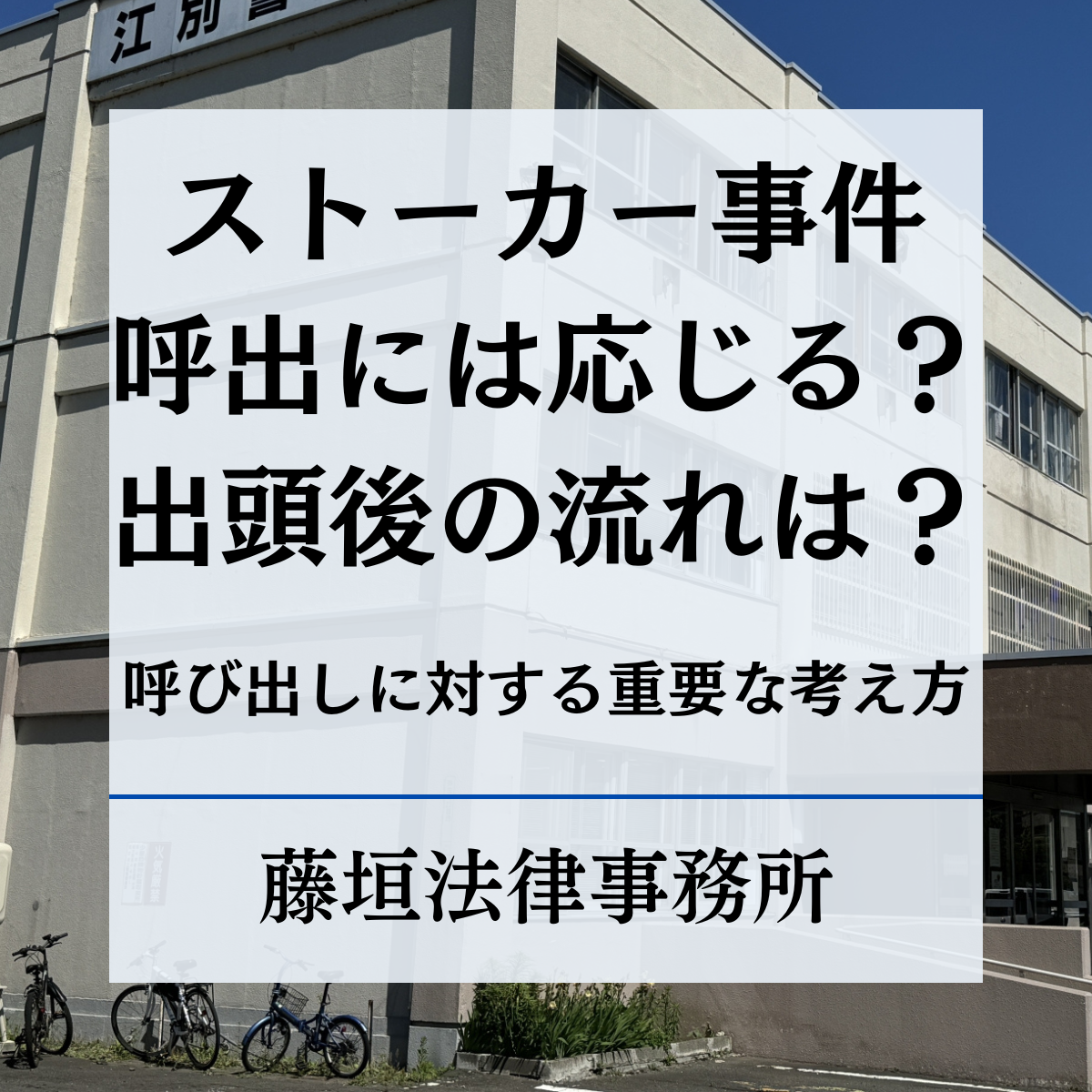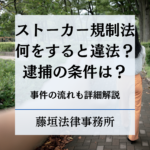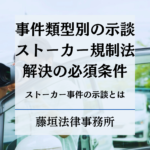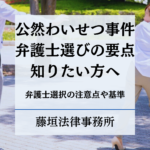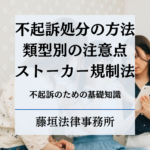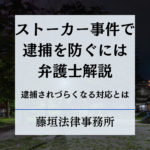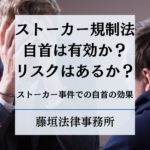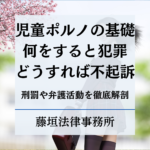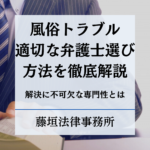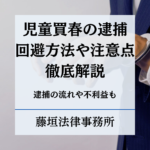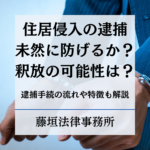このページでは,ストーカー規制法違反で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
ストーカー規制法違反に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。
LINE相談24時間受付中
ストーカー規制法違反で呼び出された場合の対応法
①行為に心当たりがある場合
ストーカーとされる行為をしたという心当たりがある場合は,まず何より逮捕を回避することを目指すのが適切です。犯罪事実の存在することが明らかである以上,捜査のために必要があると判断されれば,逮捕の危険が付きまといます。呼び出しに際しては,自らの対応で逮捕が必要との判断を招いてしまわないよう,対応方針を立てることが最優先です。
具体的には,まず自身がしてしまった行為を認め,真摯な反省の意思を表明することが望ましいでしょう。刑事事件の場合,認め事件よりも否認事件の方が逮捕の必要性が大きいと理解されるためです。
加えて,できる限り捜査機関の求めに応じて出頭する,提出を求められた証拠物は自発的に提出する,といった捜査協力の姿勢を示すことで,逮捕せずとも十分な捜査が可能であると理解してもらえるような対応を尽くす方針が有力です。
ストーカー規制法違反の場合,逮捕するかしないか,という捜査方針は呼び出しへの対応によって大きく左右されることも少なくはありません。適切な初期対応を尽くすことは,非常に大切な意味を持つと言えるでしょう。
ポイント
まずは逮捕の回避を目指す
行ったことを端的に認め,真摯な反省の意思と捜査協力の姿勢を示す
②行為に心当たりがない場合
ストーカー行為とされる内容に心当たりがない場合,捜査機関に「行為の有無をしっかり捜査しなければならない」との認識を持ってもらうことが必要です。捜査機関は,被害者と主張する人物の言い分を聞き,その内容が真実であるとの前提で呼び出していることが非常に多いため,その前提を改めてもらう必要があるのです。
そのため,呼び出しを受けた際には,まずストーカー行為に心当たりがないという点を明確に表明し,自身のスタンスを明確にしましょう。この場合,「ストーカー行為がない」という事実の裏付けとなる証拠は必要ありません。刑事事件の場合,証拠を収集する義務を負うのは捜査機関のみであって,被疑者側が証拠を集めたり提出したりするべき立場にはないためです。
そして,言い分を述べる場合には,できる限り具体的であること,一貫していることを重視するのが適切です。当事者間の言い分に相違がある場合,「どちらの言い分が信用できるか」という判断になることが見込まれますが,内容が具体的であること,一貫していることは,その言い分の信用性に大きな影響を与えます。
ポイント
相手方の言い分が真実でない可能性があるとの認識を持ってもらう
具体的な内容で,一貫して否認のスタンスを表明する
③経緯に言い分がある場合
ストーカー行為とされる行動を取ったことは間違いないが,そのような行動に至った経緯や理由について言い分がある,という場合も考えられます。
経緯に言い分がある場合の具体的な例としては,以下のようなものが挙げられます。
経緯に関する言い分の例
・突然連絡が取れなくなってしまい,やむを得なかった
・相手の一方的な態度に納得できなかった
・金銭的解決ができていない状態であった
経緯に言い分がある場合,確かに酌むべき事情もあると言えます。しかしながら,その言い分を捜査機関にぶつけて自身が正しいと主張することは控える方が賢明でしょう。
捜査機関は,犯罪事実の有無を捜査するだけの立場です。そのため,犯罪事実が存在する以上は,経緯に事情があるかどうかは捜査機関にとって関心事ではありません。経緯を捜査機関に伝えようとしても,呼び出しをする捜査機関の方に聞く意思がないため,伝えるメリットに乏しいと言わざるを得ないでしょう。
かえって,言い分を強く主張すればするほど,反省の意思がないとの評価につながり,大きな不利益につながりかねないことに注意が必要です。
経緯に関する言い分は,述べるべきタイミングや方法があります。対応を誤らないためには,弁護士への依頼を検討することが有力でしょう。
ポイント
呼び出しを行う捜査機関には,経緯を聞き入れる意思がない
経緯に関する主張は,適切な時期に適切な方法で行うべき
ストーカー規制法違反の呼び出しに応じると逮捕されるか
ストーカー規制法違反で呼び出しを受けた場合,これに応じて出頭した時点で逮捕されることは考えにくいのが通常です。逮捕をするつもりであれば,呼び出しによって予告してしまうのは証拠隠滅を招く点で不合理だからです。
もっとも,呼び出しへの対応によっては,その後の逮捕の可能性に影響を及ぼすことが考えられます。呼び出しに応じる際は,自身の対応で逮捕の可能性を高めないよう対応方針を立てることが望ましいでしょう。
この点,呼び出しへの対応によって逮捕の可能性が高くなるケースとしては,以下のような例が挙げられます。
呼び出しへの対応によって逮捕可能性が上がるケース
1.相手に接触する意思があると判断された場合
2.相手に主な落ち度がある,というスタンスであった場合
3.十分な応対がなかった場合
【1.相手に接触する意思があると判断された場合】
ストーカー事件の場合,当事者間の接触を防ぐことが捜査機関にとって非常に重要なポイントとなります。なぜなら,捜査機関に助けを求めた被害者は,今後の当事者間の接触を最も強く恐れていることが通常であるためです。
そのため,加害者側に接触の意思があると考える場合には,逮捕という強制的な手段でこれを防がなければならない,との判断に至る可能性が高くなります。
相手と会いたい,話をしたいという意思を執拗に示し続けるなど,相手に接触する意思が見受けられる場合には,逮捕可能性が高くなるでしょう。
【2.相手に主な落ち度がある,というスタンスであった場合】
ストーカー事件として問題になる場合,当事者間の関係は多かれ少なかれこじれてしまっており,修復の難しい状態になっていることが通常です。当事者間の関係が悪化した原因は様々で,どちらに落ち度があるか,当事者間でその言い分の異なる場合も少なくありませんが,関係悪化に対する落ち度への理解やスタンスが逮捕可能性を高めてしまう可能性もあります。
最も問題が大きいのは,「自分がストーカー行為をしたのは間違いないが,それは相手がに関係悪化の落ち度があるからだ」というスタンスを見せている場合です。捜査機関の目線では,自身の行為の重大性を理解できておらず,被害者側に不満をぶつける行動に出る可能性が高い,と評価されるため,逮捕の可能性を特に高くしてしまう対応方針と言えるでしょう。
【3.十分な応対がなかった場合】
呼び出しに応じて十分な応対がなく,非協力的な態度が見られる場合には,「取調べ等の捜査を行うために逮捕する必要性が大きい」との評価につながりやすいでしょう。
捜査機関が呼び出しを行うのは,呼び出せば応じてくれるということが当然の前提になっています。「呼び出しに応じてくれれば逮捕まではしなくてもよい」と考えており,適切に応じている限りは逮捕しない予定であることが多いと言えます。裏を返せば,呼び出しても応じてくれない場合,「呼び出せば応じてくれる」との期待はできないことが明らかになるため,「呼び出しても応じてくれない」可能性を踏まえた捜査手法,つまり逮捕が選択されやすくなるのです。
ストーカー規制法違反で警察が呼び出すタイミングや方法
①警告
警告は,被害者からの被害申告を受けた警察が,加害者とされる人物に対して,今後ストーカー行為をしてはならない旨を告げることをいいます。この警告は,文書が送られる形で行われることもありますが,警察署に呼び出された際に口頭で行われるケースもあり得ます。
ストーカー規制法違反の事件に関する取り扱いの中で,警告は比較的初期段階の動きとなります。そのため,被害申告があり,ストーカー行為の事実や今後反復される可能性があることなどが分かれば,それほど期間を空けずに警告のための呼び出しがなされ得るでしょう。
②禁止命令
禁止命令は,ストーカー行為をやめるよう命じる法律上の措置をいいます。禁止命令に反してストーカー行為が行われると,より重い刑罰の対象になり得るため,禁止命令は警告よりも強いストーカー抑止のメッセージと言えます。
禁止命令を行う場合には,加害者とされる側から話を聞く機会(聴聞又は意見の聴取)を設けることになるため,事前又は事後に呼び出しを受けることがあります。
禁止命令は,警告では抑止策として足りないと判断された場合の措置であるため,タイミングは警告よりも後となることが通常です。
③取調べ
ストーカー規制法違反が刑事事件として具体的に捜査される場合には,被疑者となる加害者側を呼び出し,取調べを行うことが考えられます。そのため,取調べ目的で呼び出しを受けるケースもあり得るところです。
取り調べが行われるのは,警告や禁止命令といった方法では事件が解決できないと判断した後であることが通常です。裏を返せば,警告や禁止命令で解決できたと判断する場合,取調べのための呼び出しは行われません。
そのため,取調べ目的での呼び出しは,警告や禁止命令では解決できなかった,との判断がなされた後のタイミングになります。警告や禁止命令の後にストーカー行為があった場合,再発を防止するためにもできるだけ早く呼び出す方針が取られやすいでしょう。
ストーカー規制法違反の呼び出しに応じたときの注意点
①手続の段階を把握する
ストーカー事件の場合,警告や禁止命令といった予防的な措置がある点で,他の事件類型とは異なる特徴的な手続の流れが見られます。もっとも,基本的にはどの手続であっても主に警察が対応することになるため,警察に呼び出されるということには変わりがなく,専門家以外が手続の現状を正しく把握することはそれほど容易なことではありません。
とはいえ,手続の段階に応じて見通しも違えば取るべき方針も変わり得るため,現状が手続のどの段階か,正しく把握することは非常に重要となります。
ストーカー規制法違反の手続に適切な対応を尽くしたい場合は,弁護士などの専門家に相談・依頼の上,現在位置を正しく把握しながら進めることをお勧めします。
②述べるべき主張と述べるべきでない主張の区別
ストーカー規制法違反の事件では,加害者とされる側にも一定の主張が存在しており,当事者間で主張がぶつかり合っていることは少なくありません。その中で,加害者として警察に呼び出されたとなれば,自分の主張を捜査機関にぶつけたくもなるでしょう。
しかしながら,呼び出された際に述べるべき主張とそうでない主張は,適切に区別することが肝要です。この区別があいまいなまま感情に任せて主張することは,自分に不利益をもたらしかねません。
述べるべき主張は,「疑われているストーカー行為が存在しない」というものです。まさに犯罪事実の有無に関する問題であるため,この点に主張がある場合には確実に述べることが望ましいと言えます。
一方で,述べるべきでない主張は,ストーカー行為に至った経緯や自分の気持ちという点です。これらの主張は,犯罪事実の有無に関係しないため捜査機関が参考にするものではありません。そればかりか,強く述べれば述べるほど,ストーカー行為の反復が不安視されてしまうことにもなりかねないでしょう。
③弁護士依頼の時期
ストーカー事件の場合,弁護士依頼をいつすべきか,という判断が難しい場合も少なくありません。それは,ケースによってはストーカー行為をやめるという消極的な対応以外にできることがない,という状況であるためです。
例えば,警告を受けたのみの段階であって,それ以上の手続が予定されていない状況である場合,基本的な方針は「今後相手方に接触しない」というのみです。警察としては,警告によって取り扱いを終了しているため,それ以上の積極的な動きをする機会がありません。
一方で,手をこまねいていては逮捕や刑罰を受けてしまう状況である場合も考えられるため,弁護士依頼をすべき時期にあるかは正しく理解することが非常に重要となります。
具体的な判断に際しては,弁護士に相談の上,専門的な見解を仰ぐことをお勧めします。
警察が呼び出す主な目的
警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。
①参考人である場合
参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。
参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。
②身元引受人である場合
身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。
身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。
身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。
③被疑者である場合
被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。
被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。
被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。
| 参考人 | 身元引受人 | 被疑者 | |
| 呼び出しの理由 | 事件の情報獲得 | 被疑者の出頭確保 | 犯人候補の取り調べ |
| 逮捕の可能性 | 通常なし | なし | あり |
| 前科の可能性 | 通常なし | なし | あり |
警察の呼び出しを拒むことは可能か
警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。
①参考人の場合
参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。
ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。
そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。
②身元引受人の場合
身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。
もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。
被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。
③被疑者の場合
被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。
被疑者を取り調べる方法
1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める
この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。
そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。
ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意
呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット
被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。
①逮捕を回避できる
呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。
この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。
②不適切な取り調べを防げる
警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。
この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。
弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。
③前科を防げる
被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。
この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所