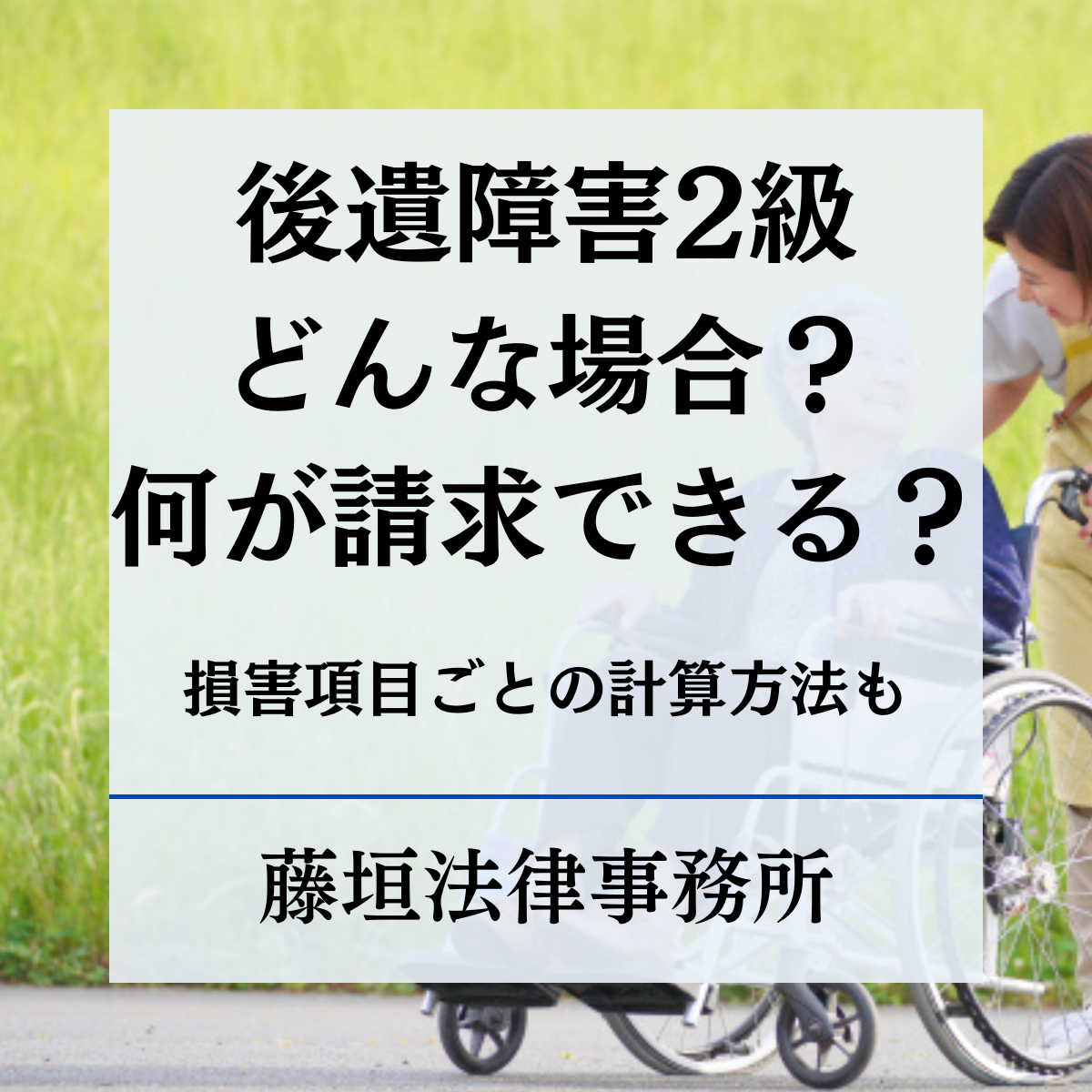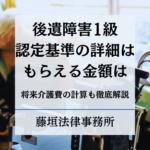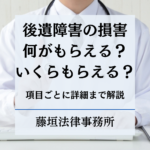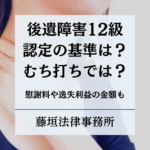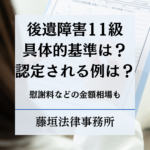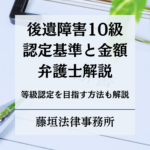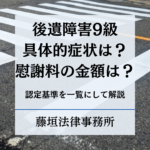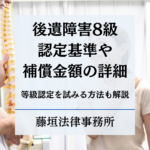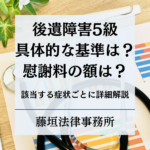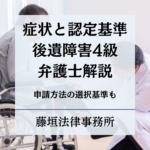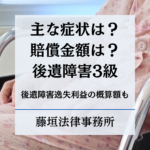交通事故の被害に遭った際,治療が終了してもなお症状が残ってしまう場合には,後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。後遺障害等級が認定された場合,受領できる慰謝料額などが大きく変わるため,等級の認定基準を把握することは重要です。
自賠責保険では,1級から14級の後遺障害等級が定められており,それぞれに詳細な認定基準が設けられています。ここでは,後遺障害2級の対象となる症状や認定の基準,認定された場合の慰謝料額などを弁護士が解説します。
LINE相談24時間受付中
後遺障害2級の認定基準
2級の認定基準一覧
要介護(別表第1)
| 要介護2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 要介護2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
その他の後遺障害(別表第2)
| 1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの |
| 2号 | 両眼の視力が0.02以下になつたもの |
| 3号 | 両上肢を手関節以上で失つたもの |
| 4号 | 両下肢を足関節以上で失つたもの |
【要介護1号】神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
脳や神経に重大な障害が残った結果,生命維持に必要な身の回りの処理の動作に随時介護を要する場合を指します。
要介護2級1号に該当する神経系統の機能や精神への障害としては,脳の器質的損傷に伴う高次脳機能障害,脳挫傷や脊髄損傷などによる身体性機能障害などが挙げられます。
具体的な認定基準は,障害の具体的な内容によって個別に定められています。
【1.高次脳機能障害】
a.重篤な高次脳機能障害のため,食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
b.高次脳機能障害による認知症,情意の障害,幻覚,妄想,頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
c.重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが,1人で外出することなどが困難であり,外出の際には他人の介護を必要とするため,随時他人の介護を必要とするもの
【2.身体性機能障害】
a.高度の片麻痺が認められるもの
b.中等度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を必要とするもの
(片麻痺:左右どちらか半身の麻痺)
(四肢麻痺:四肢すべての麻痺)
中等度の麻痺とは
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ,その基本動作にかなりの制限があるもの
(例)
・概ね500グラムのものを持ち上げられない
・文字を書くことができない
・障害のある片足の影響で,杖や硬性装具なしには階段を上ることができない
・杖や硬性装具なしには歩行が困難
高度の麻痺とは
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ,基本動作(物を持ち上げて動かす・立つ・歩行するなど)ができないもの
(例)
・完全強直又はこれに近い状態(動かない)
・上肢の三大関節(肩・肘・手)及び5つの手指すべてが自分では動かせない
・下肢の三大関節(股・膝・足)すべてが自分では動かせない
・障害を残した片腕ではものを持ち上げて移動させることができない
・障害を残した片足では,支える力や思うように動かす力がほとんどない
【3.脊髄損傷】
a.中等度の四肢麻痺が認められるもの
b.軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
c.中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
(対麻痺:両上肢又は両下肢の麻痺)
軽度の麻痺とは
障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われ,その基本動作における巧緻性や速度が相当程度損なわれているもの
(例)
・文字を書くことに困難が伴う
・概ね独歩だが,不安定で転倒しやすく,速度も遅い
・障害のある両足の影響で,杖や硬性装具なしには階段を上ることができない
【要介護2号】胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
「胸腹部臓器の機能障害」と呼ばれるものです。胸腹部の臓器に障害が残った結果,生命維持に欠かせない身の回りの処理に随時介護を要する場合に,要介護2級2号の認定対象となります。
具体的な認定基準は,臓器ごとに定められていますが,要介護2級の対象として定められているのは呼吸器の障害のみです。
呼吸器に関する要介護2級2号の認定基準は,以下の通りです。
呼吸器
a.動脈酸素分圧50Torr以下のもので,呼吸器機能の低下により随時介護が必要なもの
b.動脈酸素分圧50Torr~60Torrで,動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外(37Torr~43Torrの間にない)であり,
かつ,呼吸器機能の低下により随時介護が必要なもの
c.スパイロメトリーの結果が%1秒量35以下又は%肺活量40以下で,高度の呼吸困難があり,
かつ,呼吸器機能の低下により随時介護が必要なもの
→3級4号の基準を満たし,かつ随時介護が必要な場合に該当する
呼吸困難の程度に関する判断基準
| 高度 | 呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないもの |
| 中等度 | 呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同じように歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行ができるもの |
| 軽度 | 呼吸困難のため、健常者と同じようには階段の昇降ができないもの |
【1号】一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
失明とは以下のいずれかの場合をいいます。
「失明」とは
①眼球を失ったもの
②明暗が分からないもの
③明暗がようやく分かる程度のもの
明暗が分かるかどうかは,以下の2つの能力を基準に判断します。
・光覚弁
→暗室にて,面前でペンライト等の照明を点滅させたとき,明暗が弁別できる能力
・手動弁
→面前で手の平を上下左右にゆっくり動かしたとき,動きの方向を弁別できる能力
また,後遺障害等級の対象とする視力は,矯正視力を指します。そのため,眼鏡やコンタクトレンズなどを着用した状態の視力を基準に判断されます。
【2号】両眼の視力が0.02以下になつたもの
同様に,矯正視力を基準に判断します。
矯正視力が両眼について0.02以下になった場合,認定対象になります。
【3号】両上肢を手関節以上で失つたもの
「上肢を手関節以上失ったもの」とは
以下のいずれかの場合
1.ひじ関節と手関節との間で切断したもの
2.手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
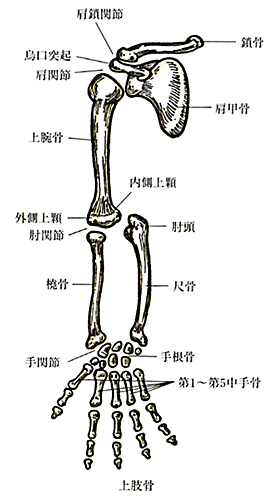
(「障害認定必携」より引用)
【4号】両下肢を足関節以上で失つたもの
「下肢を足関節以上で失ったもの」とは
以下のいずれかの場合
1.ひざ関節と足関節との間で切断したもの
2.足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
後遺障害2級の慰謝料
等級ごとの後遺障害慰謝料
| 後遺障害等級 | 【自賠責基準】 | 【裁判基準】 |
| 1級 | 1150万円 | 2800万円 |
| 2級 | 998万円 | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害2級の場合,自賠責保険からは998万円の慰謝料が支払われます。また,裁判基準の慰謝料は2370万円となります。
後遺障害2級の逸失利益
後遺障害逸失利益は,以下の計算式で算出されます。
後遺障害逸失利益
=「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
このうち,労働能力喪失率は等級ごとに設けられており,等級が上位であるほど喪失率も大きくなります。
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
後遺障害2級の場合は,労働能力喪失率が100%となります。
計算例
年収500万円,40歳,2級認定
計算式
=「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
=500万円×1.0×18.3270(27年ライプニッツ)
=91,635,000円
後遺障害2級の将来介護費
①将来介護費とは
後遺障害が残ったことにより,被害者が介護を要する状況となった場合,その介護のために発生する費用を将来介護費といいます。将来介護費の金額は,親族が行う近親者介護の場合と,業務として行う職業介護の場合とで変わります。職業介護の方が介護費用の日額が高くなるため,将来介護費の全体額も大きくなってきます。
②計算方法
【基本的な考え方】
将来介護費は,以下の計算式で算出されます。
将来介護費
=「介護費の日額」×365日×「平均余命に対応するライプニッツ係数」
基本的な考え方は,1年分の介護費を日額×365で出し,これに生涯を遂げるまでの年数を掛け合わせる,というものです。もっとも,単純に「日額×365×平均余命の年数」としてしまうと,利息の分だけ金額が大きくなりすぎてしまうという問題があります。
法律上,金銭は利息を生むものと理解されています。本稿執筆時の法定利率は年3%であるため,100万円は1年後に利息3%を含む103万円の価値になっている,というのが法律の理解です。
そのため,将来受け取るはずだったものを今受け取る場合,受け取った時点から本来受け取るはずだった時点までの利息の分だけ,早く受け取った方が得をしているという考え方になるのです。
そのため,一括で支払う場合,この期間の利息(中間利息)を差し引いた金額を支払うのが適切ということになりますが,この中間利息を差し引くために用いられる数字が「ライプニッツ係数」です。
将来介護費の計算に当たっては,「日額×365×平均余命の年数」の金額から,利息分を差し引いた金額になる,との理解をすると適切でしょう。
【介護費の日額】
職業付添人による介護が必要か,近親者付添人の介護が可能か,という点の区別によって,日額が異なります。
職業介護の場合はその実費(概ね15,000円~20,000円ほど)が日額となり,近親者介護の場合は1日8,000円ほどを日額とみなす場合が多く見られます。近親者介護よりも職業介護の方が日額は大きくなるのが通常です。
計算例
令和4年症状固定,症状固定時40歳,要介護2級認定,近親者介護
計算式
=「介護費の日額」×365日×「平均余命に対応するライプニッツ係数」
=8,000円×365日×23.7014(42年ライプニッツ)
=69,208,088円
後遺障害等級の認定を受ける方法
①手続の方法
認定手続は,加害者の自賠責保険会社に所定の書類を提出する方法で行われますが,被害者側と加害者側のどちらが提出するかによって,大きく二通りの手続があります。
1.事前認定
対人賠償保険(被害者の人身損害を賠償する加害者側の保険)が,自賠責保険会社に提出する際の方法です。自社の賠償額を算定するため,事前に後遺障害等級認定を求める手続のため,事前認定と呼ばれます。
2.被害者請求
被害者側が,対人賠償保険を通さずに自ら自賠責保険会社に提出する際の方法です。
被害者が自ら自賠責保険会社への請求を行うため,被害者請求と呼ばれます。
3.両者の違い
両者の主な違いは,以下の通りです。
| 項目 | 【事前認定】 | 【被害者請求】 |
| 提出する人 | 対人賠償保険 | 被害者自身 |
| 提出書面 | 必要書類一式 | 必要書類以外も提出可 |
| 提出物の収集 | 保険会社が行う | 被害者自身が行う |
②手続の流れ
後遺障害等級認定の基本的な流れは,以下の通りです。
【事前認定の場合】
| ①症状固定の判断 | 医師の診断などで症状固定時期に至ったことを確認します。 |
| ②後遺障害診断書の作成 | 主治医の先生へ,後遺障害診断書の作成を依頼します。所定の書式があるため,書式を持参の上で医師の診察や検査を受けるのが一般的です。 |
| ③後遺障害診断書の提出 | 相手保険に後遺障害診断書を提出します。 |
| ④事前認定の実施 | 相手保険による自賠責保険への提出を待ちます。 |
| ⑤後遺障害等級の結果通知 | 相手保険に結果の通知があり,相手保険から被害者側に知らされます。 |
【被害者請求の場合】
| ①症状固定の判断 | 医師の診断などで症状固定時期に至ったことを確認します。 |
| ②後遺障害診断書の作成 | 主治医の先生へ,後遺障害診断書の作成を依頼します。所定の書式があるため,書式を持参の上で医師の診察や検査を受けるのが一般的です。 |
| ③申請書類の準備 | 治療期間中の診断書やレセプト,交通事故証明書などの必要書類を取得し,申請書類に必要事項を記載します。 |
| ④被害者請求の実施 | 必要書類を自賠責保険会社に提出し,被害者請求を実施します。 |
| ⑤後遺障害等級の結果通知 | 申請者である被害者又は代理人に直接通知されます。 |
事前認定は,後遺障害診断書を相手保険に提出するのみで足りるため,手続が簡便であるというメリットがあります。一方で,自賠責保険に提出される資料は必要不可欠なもののみであるため,認定に有用な資料を追加で提出したい,という場合には適していません。
一方,被害者請求は,後遺障害診断書以外の提出書面も全て積極的に提出する必要があるため,手続負担が大きくなりやすいところです。しかし,提出できる資料は不可欠なものに限られず,判断に際して考慮してほしい資料や内容を任意に提出できるというメリットがあります。
後遺障害等級のうち,検査結果の数値で認定結果が決まる場合には,事前認定か被害者請求かという手段よりもその検査結果が重要になるでしょう。検査結果が認定基準を満たしている限り,どちらの方法でも差し支えないという結論になります。
一方,認定基準が数値だけでは判断できず,複数の事情を総合的に踏まえる必要がある場合,考慮してもらうべき事情を積極的に提出することが有益になり得ます。この点,必要な診断書等以外の資料を積極的に提出したい場合には,被害者請求の方法を取る必要があります。
そのため,数値で判断が可能な内容かどうかによって,事前認定と被害者請求を適宜選択することが有力でしょう。
弁護士依頼のメリット
①必要な対応を弁護士に任せることができる
交通事故被害に遭った場合,主に相手保険との間でやり取りが必要になり,その内容は多岐に渡ることが少なくありません。そのため,ただでさえ被害に遭って心身のダメージを抱えている中,相手保険への対応でさらに疲弊させられてしまうということが生じがちです。
この点,弁護士に依頼をすれば,その後の必要な対応を全て弁護士に任せることが可能です。弁護士に適切な対応をしてもらうことで,不要な負担を感じることなく解決を目指せるでしょう。
②後遺障害等級認定に必要なことが分かる
後遺障害等級認定を目指す場合,その等級認定基準を満たしていると判断してもらうことが必要になります。そうすると,あらかじめ等級認定基準を踏まえた上で,基準を満たす内容の資料を提出する形で申請を試みることが不可欠です。
しかしながら,等級認定基準を正確に把握することは,交通事故分野に精通していない限りは容易でありません。
この点,弁護士に依頼することで,等級認定基準を踏まえた申請の準備を弁護士に検討してもらうことが可能になります。そのため,後遺障害等級認定のために必要な対応が分かり,適切な申請ができるようになるでしょう。
③慰謝料などの増額が期待できる
交通事故の場合,弁護士が交渉を行うことで,慰謝料などの増額ができる場合が非常に多く見られます。これは,保険会社が,弁護士の有無で慰謝料などの賠償額を異にする運用をしているためです。
弁護士に依頼することで,慰謝料をはじめとした損害賠償額の増加が期待できるでしょう。また,後遺障害等級が認定された場合,後遺障害に応じた慰謝料なども発生するため,弁護士による増額の余地はさらに大きくなることが見込まれます。
交通事故に強い弁護士をお探しの方へ
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所